新熊野 (いまくまの) 神社 (東山区今熊野椥ノ森町)
 東大路通を泉涌寺道交差点から少し上がった西側にある神社。東大路通を挟んだ両側には「今熊野商店街」が広がり、賑やかな場所に位置するが、境内に一歩足を踏み入れるとそこには静寂で厳かな空間がある。
東大路通を泉涌寺道交差点から少し上がった西側にある神社。東大路通を挟んだ両側には「今熊野商店街」が広がり、賑やかな場所に位置するが、境内に一歩足を踏み入れるとそこには静寂で厳かな空間がある。
熊野神社、熊野若王子神社とともに 「京都三熊野社」 の一つ。
(祭神) 熊野牟須美大神(くまのむすびのおおかみ)=伊弉冉尊(いざなみのみこと)
【歴 史】
平安時代末期の永暦元 (1160) 年 後白河法皇が院政を行うために住した「法住寺殿」(現 法住寺) の鎮守社として創建される。造営には平清盛・重盛父子が当たった。
熊野信仰が盛んであった当時、一生のうちに34回も熊野参詣をしたという後白河法皇は、この鎮守社を熊野の新宮・別宮として創建。紀州の古い熊野に対する京の「新しい熊野」、紀州の昔の熊野に対する京の「今の熊野」という当時の都人の認識が社名の由来と言い、当初より「新熊野」と「今熊野」が混在していたらしい。
応安7 (1374) 年 観阿清次・藤若丸 (観阿弥・世阿弥) 父子がこの地で、大和猿楽の結崎座の興行を行う。室町幕府三代将軍 足利義満は、この興行を観て以来二人を寵愛するようになる。
応仁・文明の乱 (1467-1477年)
で荒廃。
寛文6 (1666) 年 第108代 後水尾天皇の中宮・東福門院和子により社殿が再建される。
寛文13 (1673) 年 聖護院宮道寛親王 (後水尾上皇 皇子) により本殿が再建される。

【境 内】
<樟 社>
江戸前期に建立された石造の明神鳥居をくぐると左手には、驚くほどに大きな樟がどっしりと立っている。鳥居近くには「天然記念物 新熊野神社ノ樟」の石柱。駒札には「後白河上皇お手植の「大樟 (クスノキ) 」さん」とあり、神社創建の折に熊野より移植、上皇お手植えの木という。また、熊野の神々が降臨する「影向 (ヨウゴウ) の大樟」とも言われ、人々から「大樟大権現」と尊崇されている。
その「大樟大権現」を祭神とするのが「樟社」。「樟龍弁財天」とも呼ばれ、神域として立派な門が設けられている。門前には、「大樟さんのさすり木」と名付けられた古い樟の一部が、オブジェのように置かれている。表面は多くの人々にさすられたようでツルツル。また近くには、神社全景の精巧なジオラマが置かれており、参拝の案内に役立つ。



<本 殿 (京都市指定有形文化財)>
現在の本殿は、江戸期 寛文13 (1673)年に聖護院宮道寛親王により再建されたもの。代表的な「熊野造」である熊野本宮証誠殿 (しょうじょうでん) と、構造形式、平面構成が同じで、類例の少ない「熊野造」の代表的社殿という。さらに現在の証誠殿よりも古いことから、京都市指定有形文化財となっている。
流造で正面に向拝が付く。内部は内陣と外陣に分かれる。
屋根瓦には御神鳥の「八咫烏」が左右に付されている。よく見れば嘴が「阿・吽」の形をしている。




<御神木>

本殿左右に茂るのは、御神木の「椥 (なぎ, 梛とも)」。地名が表すように、古来より椥の木が生い茂る地域だったらしく、当社は「梛ノ宮」とも呼ばれている。
神社の説明では「ナギの葉は多くの縦脈からなるので容易に切れにくいため「縁結びの樹」とされ、またナギが罪穢や災禍を「ナギはらう」に通じることから「霊験ある樹」として信仰されている」とのこと。因みに「熊野速玉大社」の御神木の梛は、樹齢約千年という日本一の巨木。熊野権現の象徴として、古来より熊野詣の道中安全を祈って人々は梛の葉を懐中に忍ばせたという。
また境内南西には、昭和55 (1980)年、成人式を迎えた今上天皇が参拝の折に植樹された梛の木 (当時樹齢20年) が育っている。
<上之社・中之社>
 本殿に参拝し社殿左手の道を行くと、上之社と中之社、二つのお社が並び建つ。
本殿に参拝し社殿左手の道を行くと、上之社と中之社、二つのお社が並び建つ。
左 「上之社」 (御祭神) 速玉之男大神(はやたまのをのおおかみ, 伊弉諾尊)・熊野家津御子大神(くまのけつみこのおおかみ, 素戔嗚尊)
右 「中之社」 (御祭神) 天忍穂耳尊(あめのおしほみみのみこと)・瓊々杵尊(ににぎのみこと)・彦火火出見尊(ひこほほでみのみこと)・鵜茅草葺不合尊(うかやふきあえずのみこと) … 天照大神以降、神武天皇に至るまで四代の神々。
<京の熊野古道>
 「上之社・中之社」の先は、境内北側の一段と高くなった一帯に設けられた 「京の熊野古道」 へと続く。「京の熊野古道入口」の案内に従って石段を上っていくと、小さな御社が西から東へと続く。それぞれの御社には新熊野神社の考える神の世界が、「熊野本宮八葉曼荼羅」を基に具象化されて展示されている。
「上之社・中之社」の先は、境内北側の一段と高くなった一帯に設けられた 「京の熊野古道」 へと続く。「京の熊野古道入口」の案内に従って石段を上っていくと、小さな御社が西から東へと続く。それぞれの御社には新熊野神社の考える神の世界が、「熊野本宮八葉曼荼羅」を基に具象化されて展示されている。
いくつか列挙すれば、「熊野曼荼羅」「熊野稲葉根王子と荼枳尼天」「八咫烏」といった具合。日本が神仏習合の国であることを強く感じさせる場所だ。
<若宮社・下之社>
 「京の熊野古道」出口の石段を下りると、本殿東側の「若宮社・下之社」に至る。
「京の熊野古道」出口の石段を下りると、本殿東側の「若宮社・下之社」に至る。
左 「若宮社」 (御祭神) 天照大神(あまてらすおおみかみ)
右 「下之社」 (御祭神) 稚産霊命(わくむすびのみこと;穀物と養蚕の神)・軻遇突智命(かぐつちのみこと;火の神)・埴山姫命(はにやまひめのみこと;土の神)・彌都波能売命(みづはのめのみこと;水の神)
<"能楽発祥の地" として>

 鳥居を入ってすぐの右手、境内東の瑞垣の傍に大きく「能」と彫られた石碑がある。応安7 (1374) 年、室町幕府三代将軍 足利義満の御前能として、大和結崎座の観阿弥とその子 世阿弥 による「今熊野勧進猿楽」が演能されたことを記念するものだ。
鳥居を入ってすぐの右手、境内東の瑞垣の傍に大きく「能」と彫られた石碑がある。応安7 (1374) 年、室町幕府三代将軍 足利義満の御前能として、大和結崎座の観阿弥とその子 世阿弥 による「今熊野勧進猿楽」が演能されたことを記念するものだ。
その隣には、日本中世史研究家として、分けても中世芸能史研究の大家として知られる林屋辰三郎氏の、碑を建立した「新熊野神社」と「今熊野猿楽復興委員会」に対する祝辞を記した副碑もある。そこには、碑名「能」の文字は、林屋氏が世阿弥自筆本「花鏡」の中から選んだこと、「猿楽」が現代の伝統芸術「能」へと完成されたその端緒が今熊野の社頭であったことなどが銘記されている。
世阿弥の芸談をもとに息子の元能 (もとよし) が著した 『申楽談儀 [世子六十以後申楽談儀 ぜしろくじゅういごさるがくだんぎ]』
には、
「観阿、今熊野の能の時、猿楽と云事をば、将軍家 (鹿苑院) 御覧じはじめらるる也。世子十二の年也」
とあり、それに続く文章からは、観阿弥・世阿弥父子の今熊野における演能が将軍義満の目にとまり、以後、能は地方の芸能から京 (中央) の芸能へとなったことが推察される。しかし、その演能地が「新熊野神社」境内であったことが定説となったのは、半世紀程前に過ぎず、演じた演目については今も解らないらしい。
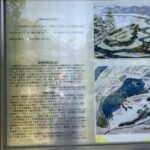
 現在当社では、地域住民や京都芸術大学などと共に産官学連携による「今熊野猿楽復活プロジェクト」を立ち上げて、当初の 「観阿弥の能」 復活を目指しているという。そこからは「神道はどの宗教よりも地域との結び付きが強く、神事は地域住民が担わなくてはならない」という当社の信念が伝わってくる。
現在当社では、地域住民や京都芸術大学などと共に産官学連携による「今熊野猿楽復活プロジェクト」を立ち上げて、当初の 「観阿弥の能」 復活を目指しているという。そこからは「神道はどの宗教よりも地域との結び付きが強く、神事は地域住民が担わなくてはならない」という当社の信念が伝わってくる。
芸術大学の学生が描いた「今熊野猿楽図」や「世阿弥義満機縁の地」と刻まれた絵入りの石碑は、プロジェクトの成果のひとつ。
<参考資料>
・ 新熊野神社 website
・ 『今熊野猿楽』 京都市歴史資料館 情報提供システム 「フィールド・ミュージアム京都」 HI008
・ 『世阿弥という人』 小山弘志 著 (ジャパンナレッジ 「古典への招待」 (第59巻 謡曲集(2)より)